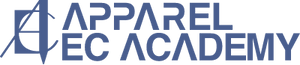アパレルECの商品撮影のポイント!撮影方法や撮影時の注意点を解説
投稿日: 投稿者:株式会社フォーピープル

アパレルECでは、どれだけ商品が魅力的でも「写真の印象」で購入率が大きく変わります。
実際、SNSやECサイトで服を選ぶときに、撮影の仕方ひとつで「高見え」したり「チープ」に見えたりすることもあります。
撮影は、商品をより良く見せるためだけでなく、ブランドの世界観や信頼感を伝える重要な要素です。
ただ、いざ撮影を始めようとすると「どんな構図がいいのか」「モデル撮影と物撮りの使い分け」「照明の設定」など、悩むことも多いでしょう。
この記事では、アパレルECの商品撮影で押さえておきたいポイントや撮影方法、外注時の注意点までをわかりやすく解説します。
EC担当者やブランド運営者の方は、ぜひ撮影品質を見直す参考にしてください。
アパレルECにおける商品撮影の重要性

アパレルECでは、実際に商品を手に取れないため、写真の印象が購入意欲を大きく左右します。どれほどデザインが優れていても、暗い写真やくすんだ色味では魅力が伝わりにくいものです。光の加減や構図を工夫することで「高見え」や「清潔感」を演出でき、結果的にブランドへの信頼にもつながります。
写真が売上やブランドイメージに与える影響
アパレルECでは、写真が購買行動を左右する大きな要素になります。実際に手に取れないオンライン販売では、ユーザーは写真を通して「品質」「サイズ感」「雰囲気」を判断します。例えば、照明が暗く色味が不自然な写真は、実際よりも安っぽく見えてしまい、購入意欲を下げてしまうことがあります。一方で、明るさや構図、モデルの雰囲気が統一された写真は、商品だけでなくブランド全体の印象を高めることができます。
また、写真の統一感があると、ユーザーが商品一覧を見たときに世界観を感じやすくなり、サイト滞在時間の向上にもつながります。ECサイト全体の見やすさや信頼感を支えるのが“写真の質”であり、ブランドの価値を伝える重要な要素といえます。
購入を後押しする「信頼感」の作り方
購入を決める際、ユーザーが重視するのは「信頼できるかどうか」です。写真が実物と近い色味であり、細部まで確認できることが信頼につながります。商品を正確に表現するためには、照明の色温度を整え、ホワイトバランスを適切に調整することが欠かせません。また、モデル着用写真では、自然なポージングや生地の動きを映すことで、着用時のイメージを具体的に伝えられます。
さらに、すべての写真に一定のトーンや背景を用いることで、ブランドらしさを保ちながら、ユーザーに安心感を与えられます。撮影のクオリティを高めることは、単にきれいに見せるためではなく、「購入しても間違いがない」と感じてもらうための信頼構築の手段といえるでしょう。
アパレルECの商品撮影で使われる主な撮影方法
アパレル撮影には複数のスタイルがあり、商品ジャンルや目的によって最適な手法が異なります。
それぞれの特徴を理解し、ブランドに合った表現を選ぶことが重要です。
- トルソーや平置き撮影:形や素材感をシンプルに伝えたいときに最適
- モデル撮影:着用感やサイズ感をリアルに伝えられる
- フラットレイ・動画撮影:SNSでの訴求にも効果的
これらを目的別に使い分けることで、撮影全体のクオリティと訴求力を高められます。
トルソー・平置き・吊るし撮影の特徴と使い分け
アパレルECの商品撮影では、商品をどのように見せるかによって撮影方法を選ぶことが大切です。トルソー撮影は、立体感を出したいときに最適で、服の形やシルエットをリアルに伝えられます。特にジャケットやワンピースなど、着用時のフォルムが重要なアイテムに向いています。一方、平置き撮影は、素材や柄、質感を細かく見せたいときに効果的です。布の流れや生地の厚みを強調できるため、ニットやカットソーの撮影にも適しています。
吊るし撮影は、自然なドレープや軽やかな印象を演出するのに役立ちます。風を当てて布の揺れを出したり、自然光を取り入れて柔らかい影をつくったりすることで、より動きのある写真に仕上げることができます。撮影方法を目的別に使い分けることで、同じアイテムでも印象を変えることができ、ユーザーに伝えたい魅力をより効果的に表現できます。
モデル撮影の魅せ方と活用ポイント
モデル撮影は、服を「着る」イメージで伝えるための最も効果的な方法です。実際の着用感やサイズ感を伝えることができるため、購入後のギャップを減らせます。モデルを選ぶ際は、ブランドのターゲット層や世界観に合っているかを意識することが重要です。たとえば、ストリート系ブランドなら動きのあるポージングを、フェミニン系ブランドなら柔らかい自然体の姿勢を意識すると、写真全体の印象が統一されます。
背景選びも印象を左右するポイントです。スタジオでの撮影はクリーンで統一感を出せる一方、屋外の自然光を活かした撮影ではリアルな着こなしを表現できます。また、カメラアングルを変えることで、脚長効果や素材の動きなどを自然に演出することも可能です。モデル撮影は「商品を魅せる」だけでなく、「ブランドの世界観を体現する」手段でもあります。
フラットレイ・動画撮影などトレンド手法
SNSの発達により、フラットレイや動画を取り入れた撮影も一般的になっています。フラットレイ撮影は、商品を上から見下ろす構図で撮影する方法で、コーディネート全体のバランスや小物の組み合わせを見せやすいのが特徴です。InstagramやPinterestなどでは、視覚的に統一されたフラットレイ写真が高いエンゲージメントを生んでいます。
また、動画撮影では、布の動きや光沢、質感の変化をリアルに伝えることができます。特にショート動画やリール形式は、SNS上での拡散力が高く、商品の使用イメージをより具体的に伝えるのに効果的です。最近では、撮影から編集までをスマートフォンで完結させるケースも増えており、スピード感を重視するブランドにも取り入れやすい手法といえます。静止画と動画をうまく組み合わせることで、ECサイトとSNSの両面でブランドの魅力を発信できるようになります。
アパレルEC撮影の準備と撮影時のポイント

撮影の品質は、事前準備でほぼ決まります。撮影環境や照明、衣類の整え方を事前に整備しておくことで、効率が上がり、修正作業の手間も減らせます。
以下のポイントを押さえると、安定した品質を維持しやすくなります。
- 光の向きと強さを適切にコントロールする
- 衣類を清潔に整え、シワや汚れをなくす
- 撮影後の編集を前提に構図を意識する
こうした準備を丁寧に行うことで、撮影全体の安定感と仕上がりが大きく変わります。
光の使い方とライティングの基本
アパレルECの撮影では、光の扱いが仕上がりを大きく左右します。明るさや陰影のつけ方ひとつで、素材の質感や商品の立体感が変わるためです。自然光を使う場合は、午前中の柔らかい光が理想的で、影がきつく出にくく、布地の色をナチュラルに再現できます。スタジオ撮影では、メインライト・補助光・背景光の3点照明を基本とし、被写体の明るさとコントラストをバランスよく整えます。
また、白背景での撮影では反射板(レフ板)を使うと、影をやわらげて全体を明るく見せることができます。逆に、陰影を強調したい場合は光源を一方向から当て、素材の凹凸や厚みを引き立てるのが効果的です。光の強さや角度を丁寧に調整することで、商品写真に深みとリアリティを持たせることができます。
スタイリング・シワ・色味のチェック方法
撮影前のスタイリングは、写真の印象を大きく左右します。服の形が崩れていたり、シワやほこりが目立ったりすると、どんなに構図が良くても品質が低く見えてしまいます。スチーマーで丁寧にシワを取る、コロコロでほこりを落とす、タグや糸の飛び出しを確認するなどの細かな作業を怠らないことが大切です。
また、色味は照明やカメラ設定によって変化するため、ホワイトバランスを整え、実物の色に近づけることを意識しましょう。撮影前にテストショットを行い、画面上の色味が商品と一致しているかを必ず確認します。加えて、トルソーやモデル着用時には、裾の折れや袖の長さなども微調整し、自然でバランスの取れた見せ方を意識すると完成度が上がります。細部まで整えることが、信頼感のある写真づくりにつながります。
撮影後の編集・レタッチで意識すべきこと
撮影後の編集では、写真の完成度を高めると同時に「実物とのギャップを生まないこと」が重要です。明るさや色調補正、トリミングを行う際も、過剰な加工は避けましょう。特にアパレルECでは、素材感や色の再現性が購買判断に直結するため、自然な補正にとどめることが信頼維持につながります。
編集段階では、画像サイズや比率を統一しておくことも大切です。商品ページ全体の統一感が生まれ、サイト全体の印象が洗練されます。また、ファイル名を「商品番号_カラー名.jpg」といった形式に揃えておくと、後のデータ管理や更新作業がスムーズになります。レタッチは写真を“飾る”ための作業ではなく、“整える”ための工程であると意識することで、自然で美しい仕上がりを実現できます。
自社撮影と外注撮影のメリット・デメリット
アパレルECの撮影を進める際、「自社で行うべきか、それとも外注すべきか」で悩むケースは多いです。どちらにも利点と注意点があり、ブランドの規模や撮影頻度、リソース状況によって最適な方法は変わります。
自社撮影はスピード感と柔軟性が魅力である一方、クオリティ管理や人材育成に手間がかかる場合があります。
対して外注撮影は高い完成度が期待できますが、コストや意思疎通の面で課題が生じることもあります。撮影の目的や予算を明確にし、状況に応じて最適なバランスを見極めることが大切です。
自社撮影の強みと運用上の注意点
自社撮影の一番の強みは、スピードと自由度の高さにあります。新作の入荷や再販など、撮影が必要になったタイミングですぐに対応できるため、販売機会を逃しにくくなります。また、社内で撮影ノウハウを蓄積できれば、ブランドの世界観を継続的に反映しやすく、撮影スタイルの統一も図れます。
ただし、撮影機材や照明設備の導入、スタッフの育成といった初期コストが発生します。特に、カメラ設定やライティング知識が不十分なまま進めると、写真の品質が安定せず修正コストがかさむこともあります。自社撮影を軌道に乗せるためには、撮影マニュアルを整備したり、プロカメラマンの指導を一度受けたりするなど、体制づくりに時間をかけることがポイントです。
外注撮影のメリットとコスト面の考え方
外注撮影の魅力は、プロによる高いクオリティと一貫した仕上がりにあります。光の扱いや構図、色再現など、専門知識に基づいた撮影が行えるため、ブランド全体の印象を大きく高めることができます。さらに、モデル手配やスタジオ準備を含めて依頼できるため、社内リソースを販促や運営に集中させやすい点もメリットです。
一方で、外注は費用が発生するだけでなく、依頼内容の伝え方によっては仕上がりが想定と異なる場合もあります。そのため、見積もり段階で「撮影点数」「納期」「修正範囲」を明確にし、参考写真やトーンサンプルを共有しておくことが重要です。定期的に同じ業者へ依頼することで、ブランド理解が深まり、より安定したクオリティを得やすくなります。
状況に応じた使い分けの判断基準
理想的なのは、自社撮影と外注撮影を目的に応じて使い分けることです。商品数が多く更新頻度が高い場合は、自社撮影を中心に運用すると効率的です。逆に、新作コレクションやブランドビジュアルのように「印象を左右する重要な撮影」は、専門スタジオやプロカメラマンに任せると良いでしょう。
また、撮影工程を分担する方法もあります。例えば、モデル撮影を外注し、平置きや小物撮影を社内で行うことで、コストを抑えつつ統一感を保てます。撮影の目的・規模・納期・リソースを総合的に判断し、自社と外注の強みを組み合わせることが、効率的かつ高品質なビジュアル制作につながります。
撮影を外注する場合の注意点と依頼のコツ

外注を成功させるには、撮影会社とのコミュニケーションが欠かせません。依頼前に目的とターゲットを明確にし、方向性を共有しておくことで仕上がりのブレを防げます。
以下のポイントを押さえるとスムーズです。
- 目的とターゲット層を事前に共有する
- 参考写真やトーンを提示して方向性を統一する
- 納期や修正範囲を明確にしておく
こうした準備をしておくことで、納品後の修正負担を減らせます。
撮影会社・カメラマン選びのポイント
外注撮影を成功させるためには、撮影会社やカメラマン選びが非常に重要です。まず注目すべきは、アパレル分野の撮影経験があるかどうかです。ファッション撮影は、一般的な商品撮影とは異なり、生地の質感やスタイリングの表現力が求められます。ポートフォリオや過去の撮影実績を確認し、自社ブランドの雰囲気に合うトーンで撮影できるかを見極めることが大切です。
また、撮影の進め方やコミュニケーションの丁寧さも信頼性を判断する要素になります。打ち合わせ時に「どのような光を使うか」「どの角度を意識して撮るか」といった具体的な話ができるカメラマンは、現場での対応力が高い傾向にあります。料金だけで比較せず、撮影の柔軟性や納期対応、修正への姿勢なども含めて総合的に評価することが、長く付き合えるパートナーを見つけるポイントです。
撮影ディレクションで失敗を防ぐコツ
外注撮影を行う際は、依頼後のディレクションが仕上がりを左右します。撮影前にコンセプトやトーンを明確に伝えることが、失敗を防ぐ第一歩です。たとえば、「SNSで映える明るいトーンにしたい」「高級感を重視したい」など、目的を具体的に共有することで、カメラマンの意図とブランドの方向性を一致させやすくなります。
撮影当日は、現場で細部を確認することも大切です。ライティングの当たり方や背景の色味、モデルの姿勢などを逐一確認しながら進行することで、後の修正コストを減らせます。また、撮影後に使用用途(EC用・SNS用・LP用など)を明示しておくと、納品データの形式や構図が整理され、運用のしやすさにもつながります。撮影を「任せきり」にせず、ブランド担当者が積極的に関与する姿勢が、高品質な写真を生み出すポイントです。
外注コストを抑えながらクオリティを維持する方法
外注撮影は品質面で大きなメリットがありますが、コストをどう抑えるかが課題になりがちです。費用を最適化するためには、撮影内容を明確に整理し、ムダをなくす工夫が必要です。たとえば、同系統の商品をまとめて撮影したり、同じ背景やライティングを使い回したりすることで、スタジオ利用時間を短縮できます。また、撮影点数が多い場合は、日数を分けるよりもまとめて依頼するほうがコストを抑えやすくなります。
さらに、編集範囲を明確に定めておくことも重要です。「色補正まで」「トリミングのみ」など、どこまでを外注側に任せるかを最初に決めておくことで、追加料金を防げます。撮影会社によっては、月額契約やボリューム割引といったプランを提供している場合もあるため、長期的なパートナーシップを前提に検討するのも効果的です。コストを意識しつつも、ブランドの世界観を損なわない範囲で品質を保つことが、継続的な撮影運用の鍵となります。
まとめ|撮影品質を高めてEC売上を伸ばそう
アパレルECで成果を上げるためには、商品の魅力を正しく伝える写真づくりが欠かせません。光の扱いや構図、スタイリングといった基本を意識するだけでも、印象は大きく変わります。撮影はブランドの世界観や価値を映し出す重要なプロセスです。自社撮影でも外注でも、「どのように見せたいか」を明確にすることが大切になります。
撮影前の準備段階で商品を丁寧に整え、照明やカメラ設定を確認しておくことで、修正作業を減らしながらクオリティを維持できます。トルソー撮影やモデル撮影、フラットレイなどの手法を理解して使い分ければ、表現の幅が広がります。統一感のある写真はブランド全体の信頼感を高め、購入意欲にもつながります。
また、撮影を外注する場合は、依頼先とのコミュニケーションを丁寧に行うことが成功の鍵です。方向性やトーンを共有し、ブランドの世界観を正確に伝えることで、より完成度の高い仕上がりになります。自社と外注の強みを組み合わせ、撮影体制を整えていくことで、効率と品質を両立できるはずです。
撮影のクオリティを見直すことは、EC全体の印象を大きく変える第一歩になります。
一方で、「自社での撮影に限界を感じている」「外注してもイメージ通りに仕上がらない」と悩む方も多いでしょう。
そんな時は、株式会社for people(フォーピープル)のアパレルEC・SNS支援事業『アパグロ』にご相談ください。
アパレル業界での豊富な経験を持つプロフェッショナルが、撮影ディレクションからビジュアル設計、ECサイトへの掲載まで一貫してサポートします。
撮影品質を高めたい、ブランドの世界観を写真で表現したいと考えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
シェア: